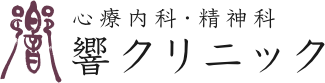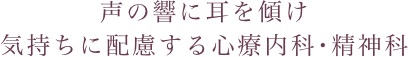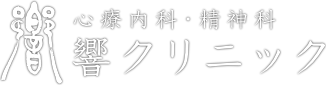ガッテン「睡眠薬で糖尿病が治療できる」に対する疑義、ベルソムラ錠
2017年04月18日
ガッテンで、2017年2月22日に表題の内容で放送がされたようです。私は番組は見ておりませんが、数人の患者さんから指摘を受け、ネットで内容を確認しました。http://www.j-cast.com/2017/02/24291584.html?p=all
科学的にはほとんど、根拠がない番組内容だったようです。NHKが、このような番組を放送したことは言語道断です。
番組で話題となった睡眠薬は、オレキシン受容体拮抗薬、商標名「ベルソムラ」ですが、2014年に発売されました。従来の睡眠薬とは、作用機序が全く違うことが特徴の睡眠薬です。従来の睡眠薬の大半は、化学的にはベンゾジアゼピン系と分類され、安定剤と共通の作用がありました。この薬は、筋弛緩作用(「足がふらつく」)や、耐性や依存性がより少ないこと(ゼロではなさそう)が特徴のようです。
実際に処方した印象としては、穏やかに睡眠を促す作用があるようです。糖尿病の治療には使えませんが、軽症の不眠症には効果が期待できます。
それにしても、NHKの番組制作姿勢には腹が立ちます。
非定型うつ病について その2
2009年09月16日
この前の続きです。
非定型うつ病は、疾患概念として確立していないと、書きました。昨年の日本うつ病学会では坂元薫先生(東京女子医大)「非定型うつ病は、うつ病か」という講演がありました。このようなタイトルで、講演がなされること自体、非定型うつ病の位置づけの不安定さを物語るのではないでしょうか。そのような疾患を、医者が未熟だと診断できない、というような論調でテレビで取り上げらる事はいかがなものかと、思うのですが。
話は逸脱しますが、新型インフルエンザはテレビでいくら取り上げられても、そのことで感染が広がることはありません。そのことを、心配して、医療機関を受診する人は増えると思いますが、その病気自体は増えることはないでしょう。精神科、心療内科領域では、その病気がひろがるように見える場合があります。これは、社会学的には、looping effectと言われている現象です。(続く・・・)
非定型うつ病について その1
2009年09月12日
昨日、「非定型うつ病」について、電話で問い合わせがありました。最近、テレビの情報番組(すっきり!)で取り上げられていたそうです。(私は、見ていません。)響クリニックでは、診断ができるか、治療ができるか、という問い合わせ内容でした。
診療中でしたので、職員が対応したのですが、改めて、お答えしたいと思います。
前者の答えは、yes and no、後者の答えは、yesです。
非定型うつ病と呼ばれる疾患概念が精神科、心療内科領域で、提唱され始めたのはごく最近のことです。
私も、いくつか論文を読んだり、本を読みました。そのような症状で悩まれている方に診察場面で出会うことは確かに増えてきました。
うつ症状と、パニック症状を併せ持ち、対人関係に敏感で、といったような人たちです。若い女性に良く見られるようです。
しかし、ひとつのまとまりのある診断単位として妥当(適当)かどうかということについては、疑問を持っています。
一般には、診断がつけば、その治療法も定まり、治療がスムーズに進みます。しかし、心の問題はそう単純ではありません。
特に、非定型うつ病は、特効薬があるわけでもなく、症状も変化していきます。
その人にどのように光を当て、どのような観点で、対応していくかは、患者さんによって千差万別です。
だから、非定型うつ病と診断することの意義(重要性)は、治療的にはさほどないように思います。丁寧にその人の話をきき、いろいろな可能性を考えながら、慎重に治療を進めていくことが大切なのは、いうまでもありません。非定型うつ病と診断するかしないかは、二次的であるように思います。続きは、稿を改めて書きたいと思います。